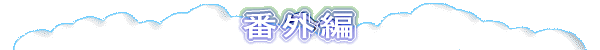
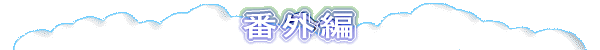
2006年10月7日8日 文庫番覚書に戻る
木曽に行ってきました。
今回、どう参加しているのか、これで何がつくれるのかなどという目先の問題から
目を洗うような、先達のあり方を学びました。木曽の山を愛し、育て、人らしい暮らしの名人です。
また、関所まつりでは、町づくりに参加するみんなが、楽しみながら、得るところもあり、
そして、人と繋がっていく宿場町の歴史の積み重ねを現代的にしていることを学びました。
昨年2005年春、木曽に行きましたが、その時知り合った方に連絡をしようかとも迷いましたが、
今回の企画には別の意味があると思いましたので、連携はとりませんでした。
今後自分の中で木曽を考える時に一体として考えられるようになると思います。
 |
ふるさと体験館の教室での学習。 木造校舎の堅牢な美しさ。 この体験館で、蕎麦うちも 機織もできます。 となりの販売所でお蕎麦と御幣餅 の昼食。 母校という言葉の再確認です。 |
 |
先頭をすたすた登る巾崎さんは、 80歳。配慮に満ちた丁寧な説明。 この手入れされた木々は ほとんどお一人の仕事。 山道は、県と村の補助で 整備できたとお聞きしました。 谷は勢いのある清冽な流れでした。 |
| 伝えるもの育てるもの | 山の主 | ||
 |
黒川荘は、古幡さんという庄屋さんの 家。ここで、食べたきのこ汁。 山のきのこを用意して頂きました。 集まってくださった、町長さんはじめ、 木曽の皆さん。すんきのお漬物。 巾崎さんの、正調木曽節、相撲甚句。 ひのきのお風呂 |
 |
PH7.5(弱アルカリ性) 硬度20(軟水) 置いてあった柄杓は 竹の枝をそのまま利用したもの 手前のわさびは自生のもの 500メートル上に水源があります。 木曽の山の中の水です。 山を守り、木を守ることが水を守ること。 |
| 宿泊した黒川荘の 囲炉裏 |
木曽の水源水 | ||
 |
今回是非見たかったのは、 木曽馬でした。 もちろん、お代官様も素敵ですが この馬の復元の歴史を 物語として読んで、絶対みたいと 思っていたものです。 |
 |
町の人のほとんどが 盛り上げる関所まつり、 長い行列は先頭の合図で 左右に振れますが、 先頭と後尾は同時とも言えません。 何事もそうですね。 沿道のお店を一軒づつ覗くのが楽しい |
| 木曽馬に乗る代官様 | 代官行列 | ||
 |
四大関所の一つ (箱根、新居、碓氷、木曽福島) しっかり覚えましょう。 これはテストに出ます!? |
 |
木曽山林高校の生徒が 関所まつりで売っていました。 プランターも自分達が作りました。と。 先達を継ぐものたちです。 よたかの星を読みたくなりました。 果たして、墨田区のベランダで 育つでしょうか。 心配を増やしてしまいました。 |
| 史跡福島関 | 木曽ヒノキの苗 |
このプログラムも短い時間での成果を求められるものではないのでしょう。
今植えた苗に300年先の木の姿を見ることができるようになりたいと思います。
清冽な水の流れのように。