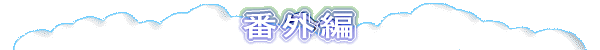
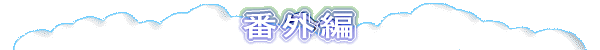
2006年11月2日〜3日 文庫番覚書に戻る
立て続けにはなりましたが、秋田県の大潟村に行ってきました。
雨水探検隊のスタッフの中で、今回行ける人ということです。第14回 秋田・ブナを植えるつどいへの参加
雨水利用国際会議の実行委員会の時以来、交流を教育部会から主に雨水探検隊の活動として、
稲の苗を提供して下さる生産者の呼びかけに対して、大潟村の水を考えることを、
墨田からしてきたことの自分なりの確認です。
同行のお二人は朝の6時40分の東京駅集合は、楽勝の方達。
やはり、朝は洗濯とおにぎりつくりをする私はあたふた。
今までのお付き合いではない方たちに受け入れてもらっている嬉しさがあります。
何事にも造詣が深く、山、歴史、水、路上、植物、人生を豊かに楽しんでらっしゃいます。私は食べ物かしら?
 |
国指定重要文化財 旧秋田銀行本店 明治42年着工 明治45年完成 外観はルネッサンス様式 内部はバロックの手法を 取り入れた建物 |
 |
ベルサイユではありません と行った事のない私は思いました。 漆喰の装飾細工の 素晴らしい天井 腰板の緑の蛇紋岩、 白大理石の階段・暖炉 地方銀行の格式の高さを実感 |
| 赤れんが郷土館 | この下で、毎日仕事! | ||
 |
秋田の稲作の四季が 展示されていました 見学に来ていた 小学生のクラスの授業 郷土の作家についても 秋田のお米についても 昔のくらしについても学べます。 |
 |
秋田は金属加工技術も すぐれています 何種類かの金属を 接合、接(は)ぎ合わせ 鍛金作品も素晴らしいのですが 手にした道具 使い込まれたものです |
| 彩色版画です | 人間国宝 関谷四郎記念室 |
||
 |
民俗芸能伝承館 三階まで吹き抜けのホール 竿灯は秋田男子の必須? ねぶり流しという、 祖先をまつる行事です 提灯は稲穂にも見立てられます 学芸員さんが、いきなり |
 |
車で登った パノラマ展望の眺めは 視界が、ほぼ360度 男鹿半島の形がくっきり 半島のくびれが羨ましかったです 足元のアザミは凛々しい色 夕日、暮れゆく一面の薄野原 |
| やってみせましょう | 寒風山のあざみ |
秋田市内と寒風山を駅レンタカーで観光しました。見所だらけ、
もちろん秋田市のマンホールの蓋は竿灯の図
ケヤキ並木とイチョウの並木が平行して色づいている道。お天気にも恵まれました。
大潟村の上に浮かんでいたのは十三夜ではなく十二夜の月でしょうか
全景が見渡せると、干拓された土地であることが良くわかりました。幻想の中を走った薄野原、
日本海へ沈む夕日。運転した方は十分景色を楽しめたかしら、外の風はやはり冷たくなってました。
 |
泊まった宿の裏手の道で 綾錦を纏うとはこのことか 巻きつかれた木は 負担になるのでしょう 綺麗な衣装で巻きつかれると 戸惑いますか? でも、自然の仕組み |
 |
役場の玄関にマンホールの蓋 何て素敵な役場でしょう その他にも各地の営林署からの 巨木の根 樹齢700年の屋久杉の根も ここは、林率全国一の町 五城目城も山の上にありました |
| 蔦の紅葉 | 五城目町役場玄関前 | ||
 |
植樹地点に上がる途中の 流れの中の岩 多くの植物が 生きていました 日本の植生の豊かさを 出発の挨拶で聞いたばかり |
 |
この岩から 山肌に向っていろいろな木から 根が伸びているのです 道を登りながら、 いのちの逞しさを思います その岩の下を 水は穿ちながら流れるのです |
| 裏に回って見ました | 何種類もの植物の根 | ||
 |
この営林署の職員の 後ろの横断幕の下で 東京方面の人で集合写真 どこかの会の植樹記念に なったのかしら 思わず、おいおい違うよと 言いそうでした |
 |
青空の下で 餅つき、バーベキュー 百五十人ほどの交流会 見えている塔は上に水を 貯める役割も 廃校になった校舎は木を多用 体育館に入ってフォルクローレ |
| 植え方を指導 | 交流挨拶 | ||
 |
昨夜から今朝にかけての 熊のうんこ ・・・・・ ・・・・・ この側に目の覚めるような紅葉 写真は?・・・・ |
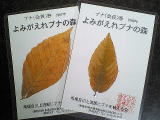 |
1000円のブナ券でこの企画に 参加することもできます 今までは、ブナ券だけでした 来て見て、学ぶことはたくさん いろいろな、ひとや組織 が、一つの取り組みのもとに はじめは、一人の思いからでも |
| これは、 | ブナ券 |
例年より紅葉は遅れているようですが、私としてはたくさんたくさん見ることができました。
植樹地に行く途中にはマタギの家の集落も。たくさんのお話も聞きたいところです。
でもすぐに雪が深くなってしまうのです。何年かの間には雨の植樹の時もあっって
急遽屋内の交流になったそうです。続いてきた活動、最初の木は高さ7メートル胸高46cmに成長
馬場目川の上流にブナの林が蘇るのは、戦後の杉一辺倒の植林をみんなで考え直すこと
一つひとつの材を知ること。一つひとつの技を知ること。一人ひとりのくらしを考えること。
いのちとは、空とは、水とは、大地とは。私を取り巻くすべてのものとの交信。
前へ 次へ 戻る![]()